小学生あるあるはよく耳にしますが、小学生の「親」もやりがちなあるあるネタを今回はご紹介します。
これを知っておくと、自分もするかもしれないと事前に心の準備ができる&事柄によっては回避するための準備もできますね。
楽しいあるある、やっちゃったあるある、あなたはいくつ経験するでしょうか?
小学生あるあるの記事はこちらです。
学用品の記名作業を甘く見積もる
子どもの物に全て記名が必要なのは園時代から変わらないので、小学生になっても大して負担は変わらないと思い気に留めない方もいます。
しかし、園時代とは学用品の量が違います。
園時代にはなかった教科書や文房具だけではなく、ありとあらゆる細々したものに記名が必要なのです!
保育園で過ごした方は服にも記名されていますが、幼稚園で過ごしていた方は制服登園だったので私服に記名しなければなりません。
筆箱の中身だけでも鉛筆や消しゴム、たくさんの小さな物が詰まっています。
入学前にはありとあらゆる全ての持ち物に記名する必要があるので、たくさんの時間を要するのです。
そして何より大変な記名作業は「算数セット」です!
「名前シールを用意してるから大丈夫」と安心している方は要注意です、この算数セットはシールを用意していても圧倒的な数の暴力で保護者を苦しめることで有名なのです…!
算数セットは数が多いことはもちろん、形も貼りにくいのです。
特に小さいおはじきと細長い数え棒は、数が多いうえに形も細かくて苦しめられる保護者が続出。
花の形をしたおはじきにはフルネームで記名できるスペースがないので、苗字と名前を分けて記名する必要もあります。
明日持って行かなくちゃいけない!なんて前日に焦ると確実に痛い目を見ます。
余裕を持って始めましょう。
また算数セットに付属の名前シールがついているものもありますが、無記名のシールなのでそれを使うには全て記名しなければならないという手間も加えられます。
算数セット用の名前シールも販売しているので、早めに用意しておくのも時短術の一つです。
またおはじきなど細かいものにシールを貼る場合はピンセットを使うと貼りやすくておすすめです。
記念写真の手が止まらない
小学生になった我が子は可愛くて可愛くてたまりません。
嬉しそうにランドセルを背負う姿や、お兄ちゃんお姉ちゃんになった喜びで自信満々な表情。
もう何度でも写真を撮ってしまいます。
入学式の朝だと、おめかしした姿も相まって写真を撮る手が止まらないでしょう!
家の前、学校の門、入学式の立て看板の横、綺麗な花壇の前、教室の前や椅子に座った姿…あらゆる場所で撮影してしまいます。
しかしあまりにも撮影しすぎ&各スポットで撮りたいがために並んで待っていると、子どもが飽きて「もういい」とせっかく順番待ちしていた列から脱してしまうこともあります。
親と子の温度差を感じられる入学式になるかもしれませんね(笑)
ちなみに入学式の時期は桜が散っている地域がほとんどなので、桜が咲いている入学前にランドセルを背負って学校まで撮影に行く人もいるそうです。
確かにランドセル姿と桜の写真は撮りたいですよね。
その際は無断で学校の敷地内に入ったり他の児童が通学している時の妨げにならないよう配慮しながら撮影を楽しみましょう。
学校にこだわらず、桜の名所にランドセルを持っていき撮影してもいいですね。
特に公園などでは低い位置に咲いている桜もあるので、桜を写そうとして引きの写真しか撮れない…という問題も解消してくれて桜の花と子どもというアップの写真も狙えます。
絶好のロケーション撮影スポットを探してみましょう!
ランドセルの重さに驚く
ランドセルを最後に背負ったのはいつですか?
もうランドセルの重さを覚えていないという方がほとんどではないでしょうか。
子どもと一緒にランドセル選びに行った時に、久々にランドセルを手にしたという人もいますよね。
ランドセル選びの時にランドセルを持って「重たいな」と感じた人もいれば、「意外と軽いな」と安心した人もいるかもしれません。
しかし、それは中身が入っていないランドセルです。
授業が始まるとランドセルには筆箱、教科書、ノート、給食セットなどたくさんの物が入ります。
準備が終わったランドセルを持つと、あまりの重さに「重っ!」と声が出てしまう方がたくさんいます。
最近ではタブレット学習がメジャーになり、タブレットを毎日持ち歩いて登下校する小学生もいます。
子どもの負担にならないよう、ランドセル選びは軽さも必ず重視したいですね。
新しい服を用意
小学校に入学したし、新しい門出に新しい服を!新しい友達もできるだろうし素敵な姿を!
などなど、入学を機に服の購入が増えてしまうことも。
特に入学したての時期は新しい服を着てほしいという願いから、つい用意してしまいます。
しかし親の思いとは裏腹に、子どもは自分が気に入った服を着て行きます。
新しく買った服を着てほしくて出していたにもかかわらず、子どもが自分で服を選びなおしていつもの服を着るなんてことも。
親が「新しい服を着てほしい」という思いと一緒で、子どもも「お気に入りの服を着て行きたい」という思いがあるのでしょうね。
特に入学したての時期は「第一印象を良くするために」という思いもありますよね。
その方法が親は「新しい服」、子どもは「お気に入りの服」なのでしょう。
新しく服を購入するのであれば子どもに選んでもらい、「お気に入りの新しい服」を着て新学期を気持ちよくスタートできるといいですね。
ちなみにこのあるあるは修学旅行前にも発生します。
「今日はどうだった?」連発
小学校に入学して新しい環境になると、子どもがどう過ごしているか気になりますよね。
新しい友達はできたか、楽しく過ごせているか、授業で取り残されていないか…子どもの様子を知りたいのは当然のことです。
しかし根掘り葉掘り聞かれると、子どもも少し辟易気味に。
子どもから嬉しそうに話してくれたらたくさん聞きましょう。
でも親から「どうだった?」「何があった?」と毎日のように聞かれては、子どもも答えるのが大変です。
「今日の仕事どうだった?」「家にいるとき何かあった?」と毎日聞かれると、大人でも負担に感じませんか?
しかも「どうだった?」という質問はとても抽象的で、子どもにとって答えることが難しいのです。
答え方がわからず、とりあえず「楽しかった」しか言わないことも考えられます。
本心の「楽しかった」なら良いのですが、答え方が分からないからと毎日同じ答えでは本当の知りたい姿を見つけられません。
もし気になって知りたいことがあれば、ピンポイントで「今日は誰と遊んだ?」「何の授業が楽しい?」など、答え方が分かりやすいように尋ねてみましょう。
ですが聞かれてばかりでは負担に感じる子どももいるので、子どもの様子に応じて問いかけましょう。
小銭欲しさに朝一コンビニダッシュ
入学前は何かと購入品が多いです。
文房具など指定がなく自分で購入できるものはいいですが、直接学校で購入するものはリストとともに「釣銭のないようご準備ください」と書かれていることもあります。
当日の朝に準備しておこうと思い財布を開けたら小銭がない…なんてことも。
朝一番にお札を崩すためコンビニにダッシュした、なんてエピソードも耳にしたことがあります。
また学用品の購入は入学前だけに限りません。
学期途中で請求される学用品や行事代の徴収に備えて、小銭を保管できるコインケースがあるともしもの時も安心ですね!
資源ごみを無理やり作る
図工などが始まると、この作業をする親も増えるのではないでしょうか。
「ペットボトルの蓋ちょうだい」
「トイレットペーパーの芯いる」
「何か空き箱ない?」
「プリンとかヨーグルトのカップ欲しい」
「いらない服持ってきてって~」
など、図工の材料を家から持ってくるように言われることがあるのです。
「来週使うから」と子どもが前もって教えてくれたのであれば、当日に向けて溜めておくことができます。
しかし、当日の朝にお願いしてくる場合があるのです。
大人は「ペットボトルの蓋が必要なら中身を飲んでしまおう」など使い切るまでに過程があることをわかっていますが、子どもは「家にある」としか認識しておらず言ったらすぐに出てくるものだと思っているのかもしれません。
そうなるともう無理やり作り出すしかありません。
ペットボトルは蓋だけ外し口が開いたまま冷蔵庫で立たせ、トイレットペーパーは全て手で巻いて別の容器に入れ、箱に入っていた中身は出され、プリンやヨーグルトは急いで食べてすぐ洗い、いらない服を探すため急いでタンスを漁る…。
不要なものをリサイクルして楽しもう!というコンセプトかもしれませんが、必要なものから不要なものに作り替えなければならない瞬間がいつか来るかもしれないと覚悟しておきましょう。
資源ごみは別で分けておき、一定分だけストックしておくのも方法ですね。
油断できないことがいっぱい

子どもが小学生に入り親の手を少し離れたことから、気を抜いてしまうかもしれません。
しかしまだまだ子どもであり、見通しも甘いのです。
子どものフォローをする形になりますが、たくさんのあるあるを経験して親子で成長していきましょう!
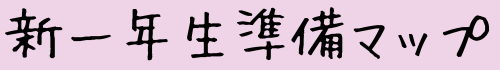
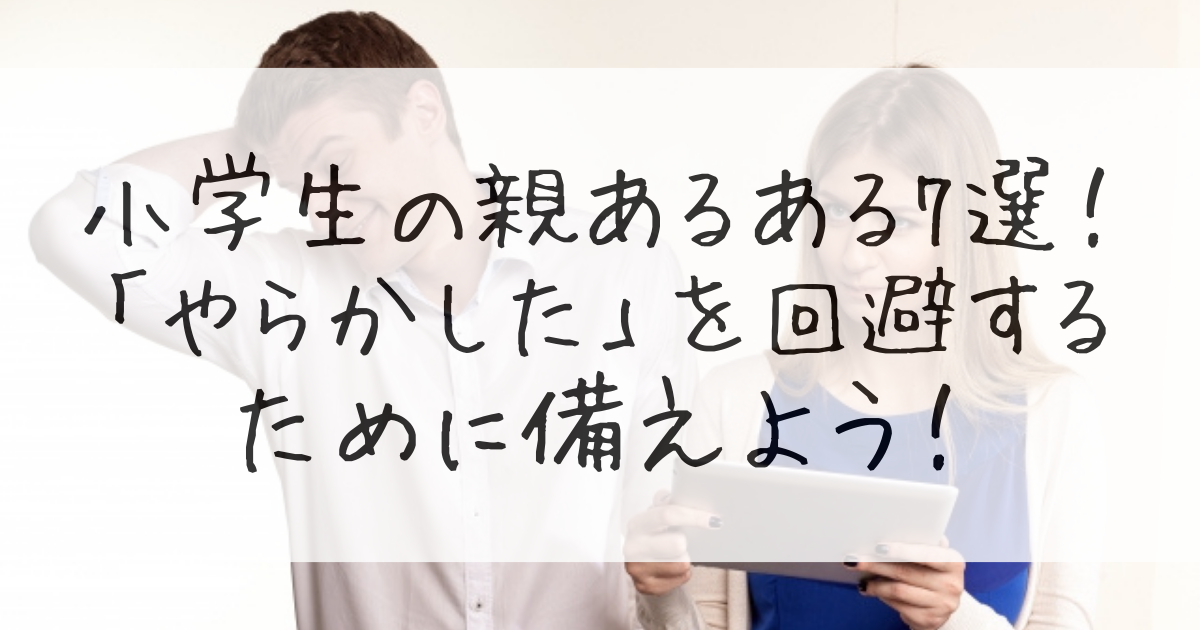
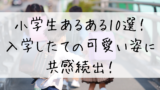

コメント