お子さんが小学校に入学すると、親御さんの生活スタイルも大きく変わります。
特に共働きのご家庭では時間の制約がありますから、学校生活へのサポート方法も工夫が必要になります。
小学校に入学したらどのような負担が増えるのか、何をサポートすればいいのかを事前に確認して心の準備をしておきましょう。
PTA活動は自分のキャパシティを考慮して
PTA活動は子どもの学校生活に対する理解を深め、学校との協力体制を築くための重要な手段です。
しかし共働きや面倒を見る家族がいる方の場合は、なかなか時間を割けませんよね。
大切なのは、自分が参加できる範囲で貢献することです。
会合への出席が難しい場合は、文書での意見提供や週末のイベントに限定して参加するなど、自分の状況に合わせた形で関わる方法もあります。
PTA役員への立候補は避け、具体的な活動やイベントのサポートに絞ることも一つの方法です。
ママ友・パパ友は情報キャッチのツール

共働きの家庭では、他の保護者との交流を深める時間がなかなか取れないこともあります。
しかしママ友やパパ友との繋がりは、子どもの社会生活における様々な情報源となるため、非常に価値があります。
自分と相性の良い数人とだけ深い関係を築くことで、ストレスを感じることなく情報交換を行えます。
メッセージアプリを利用すると時間と場所を選ばないので、直接会って話すよりも負担が軽くなります。
子どもが参加する部活動や習い事のスケジュールの共有、緊急時の連絡手段としてグループチャットを設定するなど、効率的なコミュニケーションを心がけましょう。
勉強できる環境を整えることで学習サポートを

共働きの家庭では子どもの学習サポートに割ける時間が限られていますが、質の良い学習時間は用意したいですよね。
子どものために勉強スペースを整えたり学習プランを一緒に立てたり、子ども一人でも勉強に取り組める環境づくりを意識しましょう。
オンライン学習プログラムやアプリを活用すると、親が直接教えることができない時間帯でも子どもが自習することができます。
定期的な進捗確認を行い、子どもの頑張りを感じた時はしっかりと褒めて今後のやる気に繋げていきましょう。
近年では子どもの送り迎えを推奨する小学校も

最近では子どもの送り迎えを推奨している小学校も多くあります。
特に入学したての頃は親も不安でしょうし、慣れるまでは付き添っていきたいと思う方もいますよね。
送り迎えは子どもの安全と規則正しい生活リズムを確立するために不可欠ですが、共働きの親にとっては大きな負担となりがちです。
この負担を軽減するために、近隣の家庭と送り迎えを分担する方法もあります。
子どもが自立して一人で通学できるようになるまでの安全なルートの確立、通学グループの形成などを検討しましょう。
GPS機能がついた防犯ブザーもあるので、それを持たせることで子どもの安全情報を確認することも方法の一つです。
子どもが一人で用意できる習慣を

時間がないと子どもの用意をしてしまうこともありますが、子どもが用意にかかる時間を逆算してそれに合わせて早めに起こしたり、早く食べられる朝ご飯を用意したりするなどして、自分一人で出発までの用意ができるように援助しましょう。
子どもに自己管理のスキルが身につくと、親のサポートが限られている時間帯でも自分で課題に取り組むことができるようになります。
自分のことは自分でするのが当たり前、と当事者意識が持てるように家庭でも取り組んでみてください。
いつか親より友達を優先するようになるその日まで

特に共働きの家庭では、子どもと一緒に過ごす時間が限られているので大切にしたいですよね。
夕食の時間を家族でのコミュニケーションの場にする、週末には家族でのアウトドア活動や文化活動を行うなど、家族としての絆を深める時間を有効に活用しましょう。
もちろんそれは親の心と体に余裕がないと難しいので、疲れている時は休息して一緒にまったり過ごしながら話をするという方法でも。
今はまだ親と過ごす時間が多いですが、これから子どもはどんどん親から離れて友達を優先するようになります。
それも子どもの自立の一つです。
寂しいですが子どもが親から離れていくのはすぐですので、なるべく子どもが小さなうちにたくさん思い出を作ることをおすすめします。
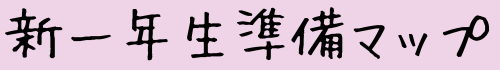
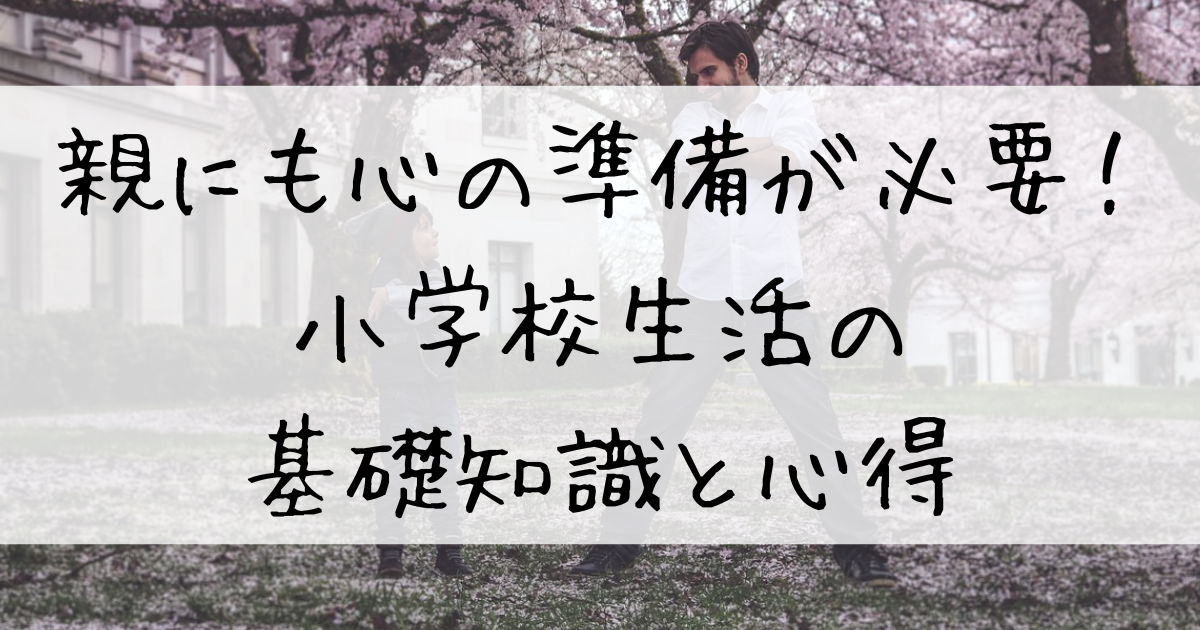
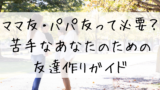
コメント